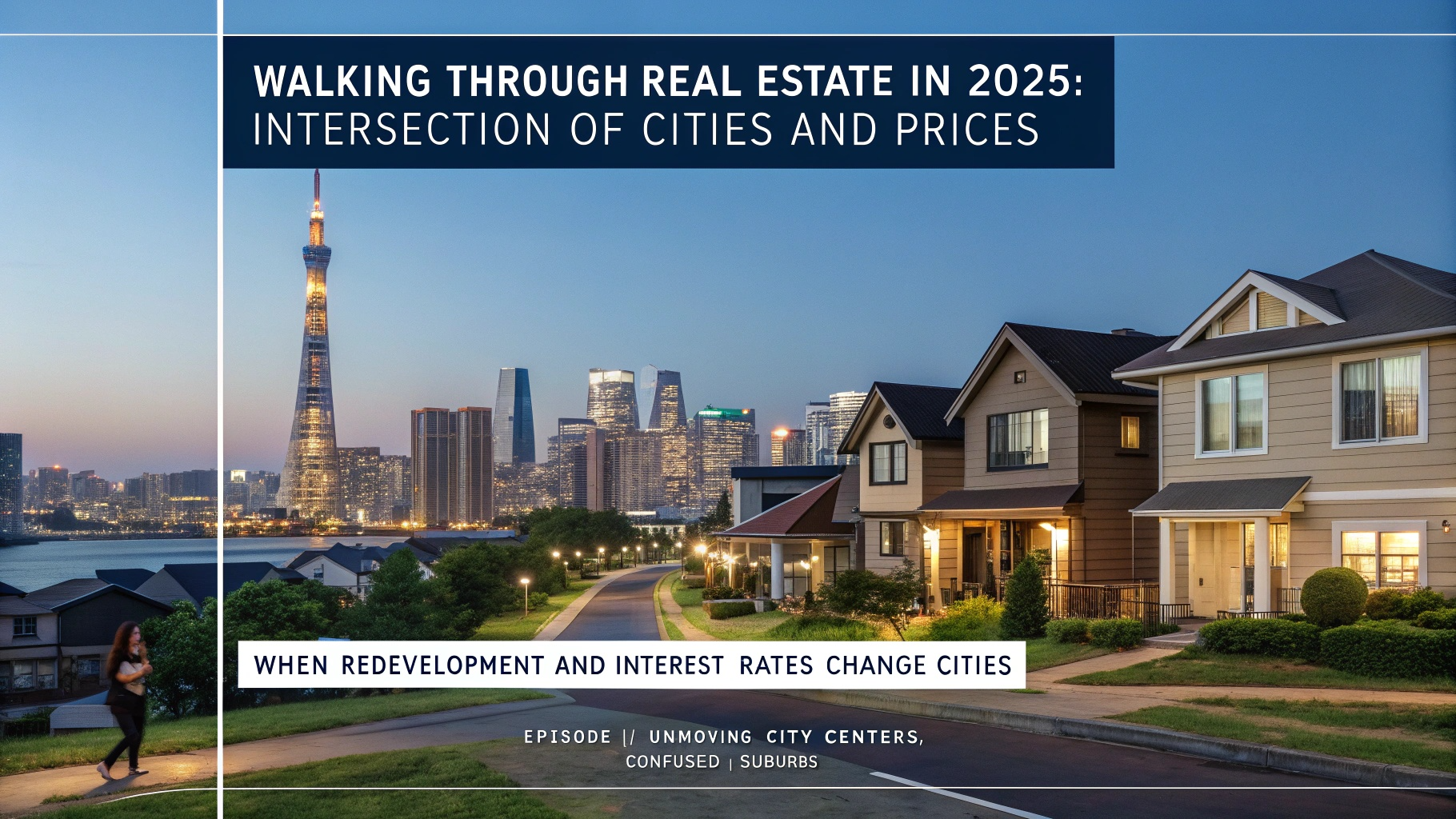― 再開発と金利が都市を変えるとき
🏙️ 第1回|首都圏の二極化
動かぬ都心、迷う郊外。2025年、東京圏の本音
「東京はいつまで上がり続けるのか?」
2025年春。東京23区のマンション価格は、ついに1億円の大台を突破した。
といっても、すべてのマンションがそうなったわけではない。
70㎡換算での平均希望価格が「1億円を超えた」ということである。これは調査史上初の記録だ。
エリアは主に港区・中央区・渋谷区など、いわゆる“超都心”に集中している。
一方、東京を取り巻く外縁部や郊外エリアでは、異なる風が吹いている。
埼玉県の平均価格は2025年に入り前年比6.2%も下落し、再び「買い手市場」の様相を呈しはじめた。
首都圏全体の地価は一見すると上昇傾向だが、実際には「価格が伸びる街」と「価格が止まりはじめた街」の二極化が始まっている。
23区が上がり続ける理由。それは“金利ではなく、価値”の話だ
「金利が上がってきたから、そろそろ不動産価格は下がるのでは?」
そう考える人は多い。たしかに、2025年に入り住宅ローン金利はじわじわと上昇を続けており、特に変動型ローンを選んできた層には不安材料となっている。
だが、東京23区のような高額帯エリアでは、金利の影響を受けにくい層が価格を牽引している。
- 海外投資家の現金購入(円安の後押し)
- 企業経営者や富裕層の住み替え
- 賃貸利回りではなく“希少性”への資金流入
このように、“自分が住むための家”ではなく“価値を持つ空間”としての不動産に、資金が集まり続けているのが23区の現実である。
郊外の価格はなぜ下がり始めているのか?
一方、郊外。たとえば埼玉県や多摩地域、千葉県西部などでは、価格の天井感が漂っている。
- 金利上昇によりローン審査が厳しくなった
- 建築費・人件費の上昇が供給価格を押し上げている
- しかし買い手の「実質賃金」が伸びていない
つまり、“払える人”が減ってきたのである。
これは市場が健全化しているという見方もできるが、同時に「値段が下がらなければ売れない」局面に入りつつあることを意味する。
成約は伸びているのに、価格が追いつかない
興味深いのは、成約件数はむしろ増えているという事実だ。
首都圏全体の中古マンション成約件数は、2025年2月時点で前年比+23.9%。
特に横浜・川崎エリアでは+34.2%と、活発な取引が続いている。
だが、それと同時に㎡単価は前年比▲1.5%と、値下がり気味。
これは何を意味するのか?
一言で言えば「値段を下げた物件が売れている」ということだ。
高く出していた物件が、価格調整をしてようやく動いた。
つまり、**“動いているからといって、市場が強いとは限らない”**のだ。
読者のあなたへ――“資産”か、“住まい”か
港区のあるタワーマンションでは、築10年の3LDKが2ヶ月で1億4,000万円で成約した。
一方、郊外の築25年・駅徒歩15分のマンションは、売り出しから半年以上が経過し、ようやく「500万円下げてもよい」との決断が出た。
同じ首都圏。だが、見ている景色はまるで違う。
「売るなら、もう少し待ったほうがいい?」
「それとも、動けるうちに選択肢だけでも持っておくべき?」
2025年は、そんな“判断の岐路”に立つ年かもしれない。
次回予告
第2回|横浜は“全部”上がっているわけじゃない
― みなとみらいと港南台、数字で見るリアルな差


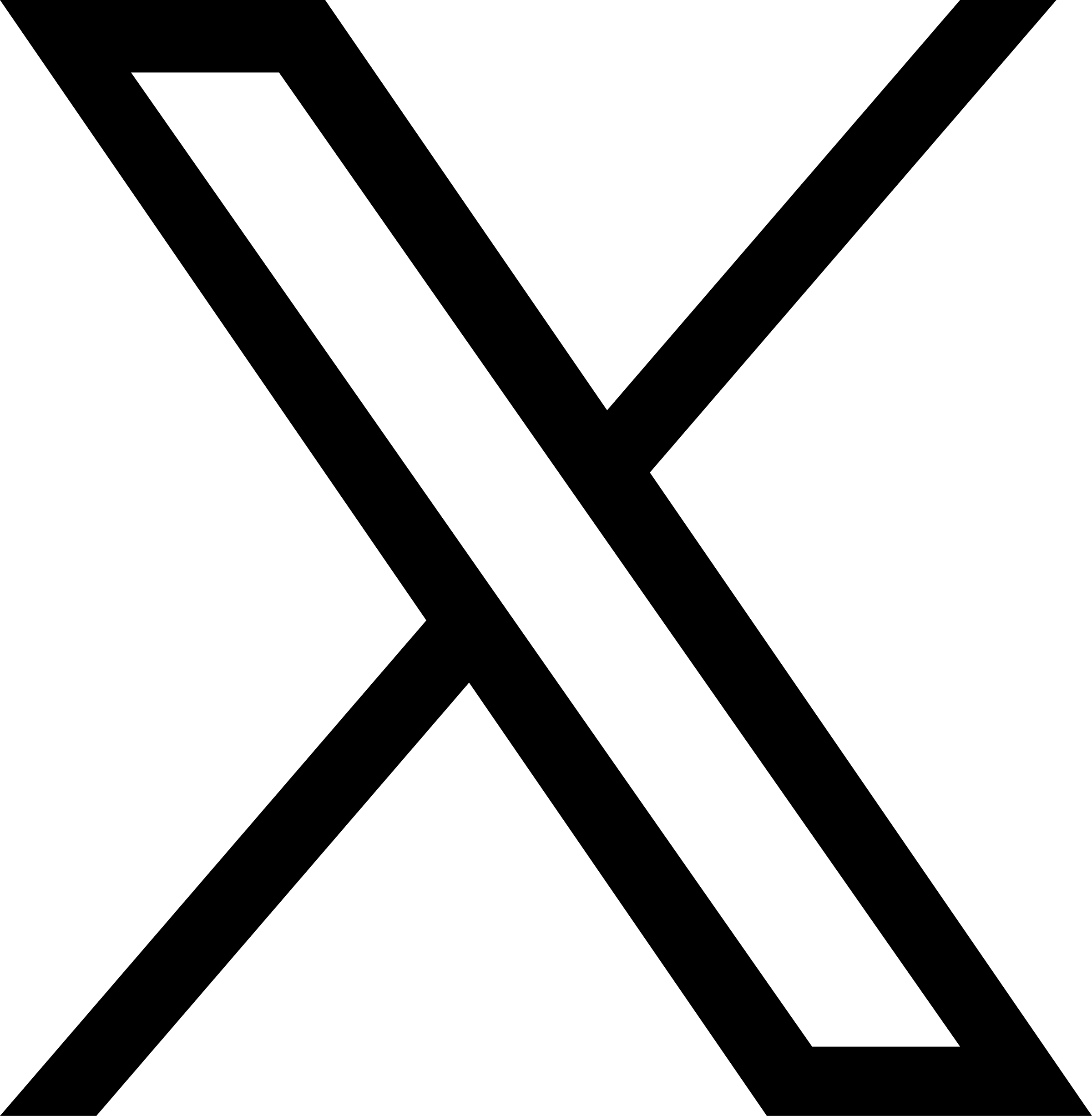

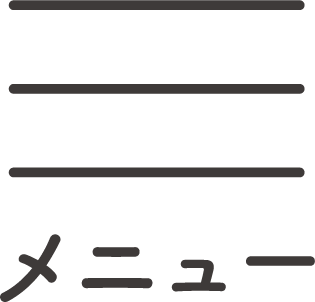

 2025年7月25日
2025年7月25日