「お盆」が壊れていく――それでも人は、どこかへ帰りたい
季節コラム
「お盆」が壊れていく――それでも人は、どこかへ帰りたい
「今年は帰らないよ。家、もうないし」
「墓じまいしたからさ。向こうの人たち、もう来なくていいって思ってるかもね」
そんな言葉が、2025年の夏に、静かに、しかし確実に広がっている。
お盆。
この国で長らく受け継がれてきた「帰る文化」。
親の待つ家に、兄弟姉妹が集まり、仏壇に手を合わせる。
迎え火、提灯、精霊馬。
そうした一連の風景が、今、音もなく崩れていっている。
きっかけはコロナだった。
3年帰れない夏が続き、それをきっかけに「帰らない」が“普通”になった。
親の側も無理を言わなくなった。
そして、気づけば――「帰るべき場所」がなくなっていた。
地方の実家は売却された。
寺は後継ぎがおらず廃院になり、墓じまいが進んでいる。
誰かの“死”をきっかけに集まっていた家族は、やがて“縁”ごと風化していく。
この十年で、「帰省」とは、もはや“実家への訪問”ではなく、
“人生のなかで失われつつある自分の一部を再確認する行為”になったのかもしれない。
SNSを見れば、旅行や音楽フェスの投稿がにぎわう。
「推し活お盆」「夏の聖地巡礼」――そんな言葉もある。
移動はあっても、心は帰っていない。
それを“自由”と呼ぶか、“喪失”と呼ぶか。
一方で、誰もいない実家の窓を開けにだけ帰る人がいる。
駅から離れた墓地の草を刈りにだけ行く人がいる。
「誰も見ていないのに、なぜそこまで?」
――そう思う人もいるかもしれない。
けれど、彼らは「誰かに見せる」ためではなく、
「自分自身の中に残したいもの」を守るために帰っている。
ある人にとって、それは「におい」かもしれない。
蚊取り線香と畳の匂い、仏壇のロウソクのにおい。
あるいは、風鈴とラジオと冷蔵庫の音の重なりかもしれない。
その“重なり”が、自分がどこから来て、何を受け継いできたかを思い出させる。
人は、帰る場所を失ったとき、
初めて「帰りたかった気持ち」に気づくのかもしれない。
でも、それでもまだ――
人は「誰かの心に帰る」ことができる。
遠くにいる友人に連絡を取る。
久しぶりに兄弟と電話してみる。
あるいは、自分の子どもに、小さな迎え火の話をする。
帰ることは、移動ではなく「想い」の循環だ。
そしてそれは、家がなくても、墓がなくても、つながることができる。
お盆が“行事”ではなくなったこの時代に、
私たちは、“何のために帰るのか”を初めて問われている。
編集後記
この国では、文化が壊れてからでないと“価値”に気づけないことが多いようです。
壊れかけたお盆の風景の中で、あなたが「守りたい」と思ったものは何ですか?
それが、あなたが“帰りたい場所”なのかもしれません。


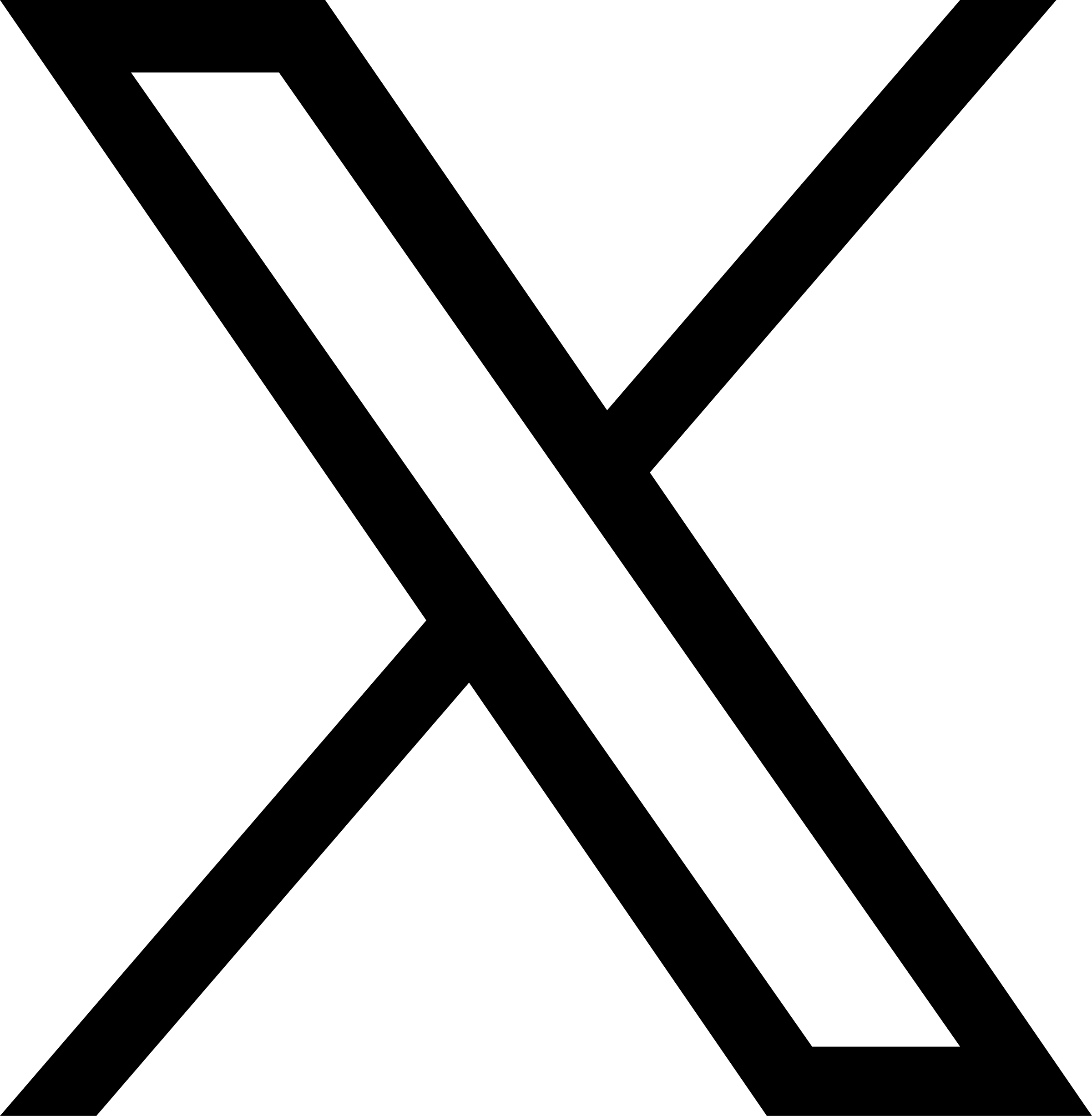

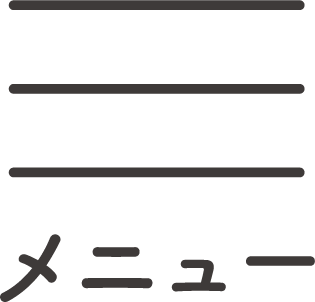

 2025年8月5日
2025年8月5日



