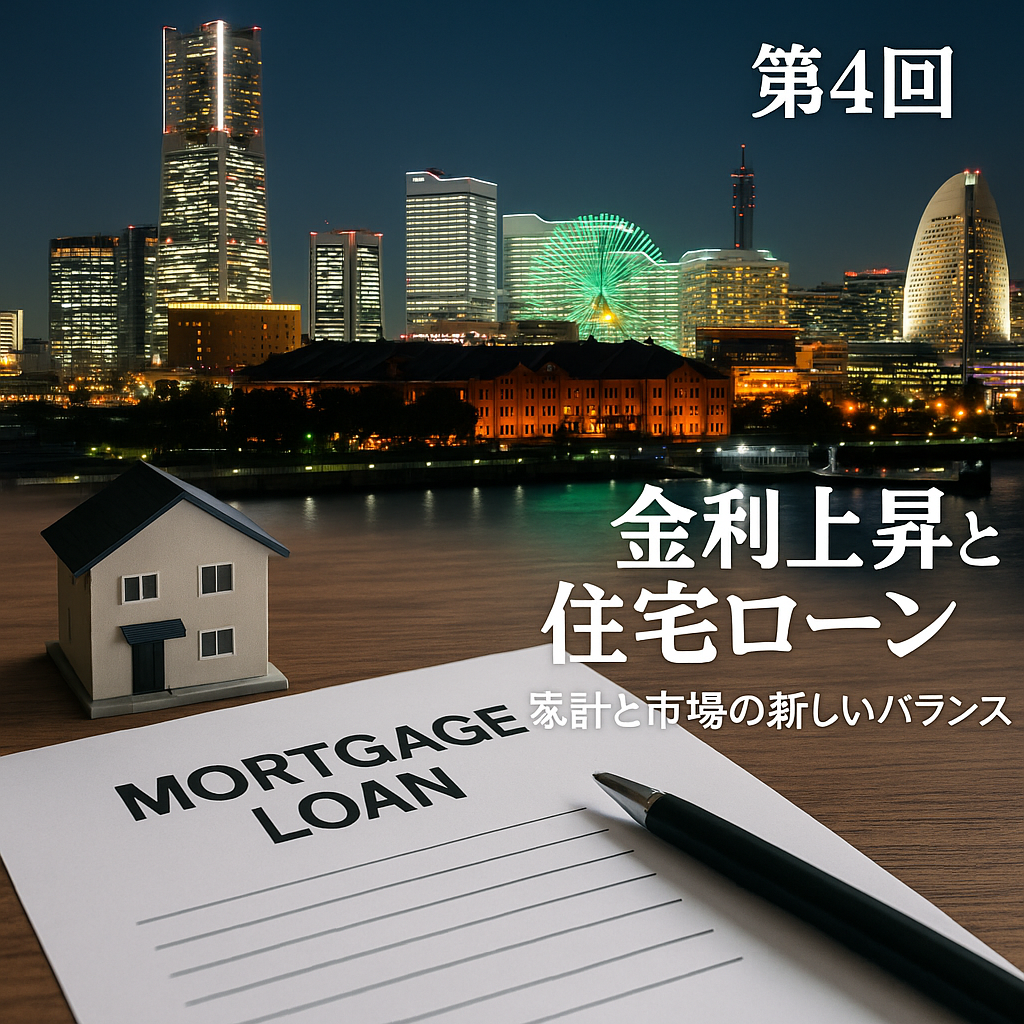🏦 第4回|金利上昇と住宅ローン ― 家計と市場の新しいバランス
住宅ローンに漂う新しい不安
「毎月の返済が、急に重たく感じるようになったんです」
港北ニュータウンで築10年のマンションを購入したばかりの30代夫婦は、そう打ち明ける。
理由は、日銀の政策変更に伴う金利上昇だ。これまで低金利を前提に計画を立てていた住宅ローンは、ほんの数%の上昇でも家計にずしりと響く。
横浜市内の不動産市場を見渡すと、新築分譲は依然として強気の価格設定を維持している。だが、購入者側は「借りられる額」に制約を受け始め、現場では価格と家計のせめぎ合いがじわりと表面化している。
金利が上がると何が変わるか
住宅ローンは金利1%の違いで、総返済額が数百万円単位で変わる。
たとえば3,500万円を35年ローンで組んだ場合、
- 金利0.5%なら:総返済額 約3,650万円
- 金利1.5%なら:総返済額 約4,310万円
差は660万円にも及ぶ。
この現実は、購入検討者の心理を大きく揺るがす。
「予算を下げざるを得ない」「買いたいエリアを変える」——そんな声が増えている。
横浜市場における影響
横浜の中心部や再開発エリアは依然として強気だが、郊外や中古市場では明らかな変化が見え始めた。
- 新築マンション:売主は価格を下げにくい → 供給数を絞り、販売戦略で調整
- 中古マンション:買い手が融資額を抑えるため、価格交渉が増加
- 戸建市場:金利負担増により「新築より中古」「横浜より県央へ」と購買行動がシフト
特に子育て世代は、返済負担の上昇に敏感だ。これまで「少し背伸びして横浜市内」を選んでいた層が、「無理せず県央や湘南へ」と方向転換するケースも目立つ。
データで読む「金利と価格」
横浜市の平均分譲価格(2025年上期)
- 新築マンション:平均6,800万円(前年比+2.5%)
- 中古マンション:平均4,450万円(前年比+0.8%)
日銀短観・長期金利(2025年8月)
- 長期金利:1.05%(前年同月比+0.4pt)
- 住宅ローン固定型金利:1.8%〜2.2%水準へ上昇
データからは「価格は高止まり」「金利は上昇傾向」「購買力は低下」という三つ巴の状況が浮かぶ。
この矛盾が市場を動かす最大の要因になっている。
今後の展望
短期的には、再開発エリアの需要が市場全体を支え、価格はすぐには崩れない。
しかし、中期的には「金利上昇による購買力低下」と「売却希望物件の増加」がじわりと効いてくるだろう。
すでに現場では、「家は買いたいが借入額は減らしたい」という声が増えており、結果として郊外・県央・中古市場に流れる傾向が強まっている。
価格が維持されるのか、それとも需要の分散で調整に向かうのか、横浜の市場は新しい分岐点に立たされている。
まとめ|“借りられる力”が市場を決める
これまで横浜の市場を支えてきたのは「低金利の追い風」だった。
だが、その環境は終わりを告げようとしている。
これからの市場では、「いくら借りられるか」ではなく「いくら返せるか」が判断基準となる。
つまり、家計の現実と市場価格のバランスが真正面から問われる時代に入ったのだ。
横浜の街は再開発で華やぎ、県央や瀬谷も未来の可能性を秘めている。
しかし、そのどのエリアであれ、最終的にマーケットを動かすのは家計の持続力だ。
都市のブランドと数字の高騰に惑わされず、「生活としての不動産」を見極める力が求められている。
編集後記
今回の取材で印象的だったのは、若い世代が「買うべきか、それとも待つべきか」と揺れていたことだ。
ローン返済は数字の問題であると同時に、家族の未来設計そのものでもある。
金利の小さな数字の変化が、街の選択や人生の方向まで左右する。
改めて、不動産とは「数字と暮らし」が交差する場所だと実感させられた。


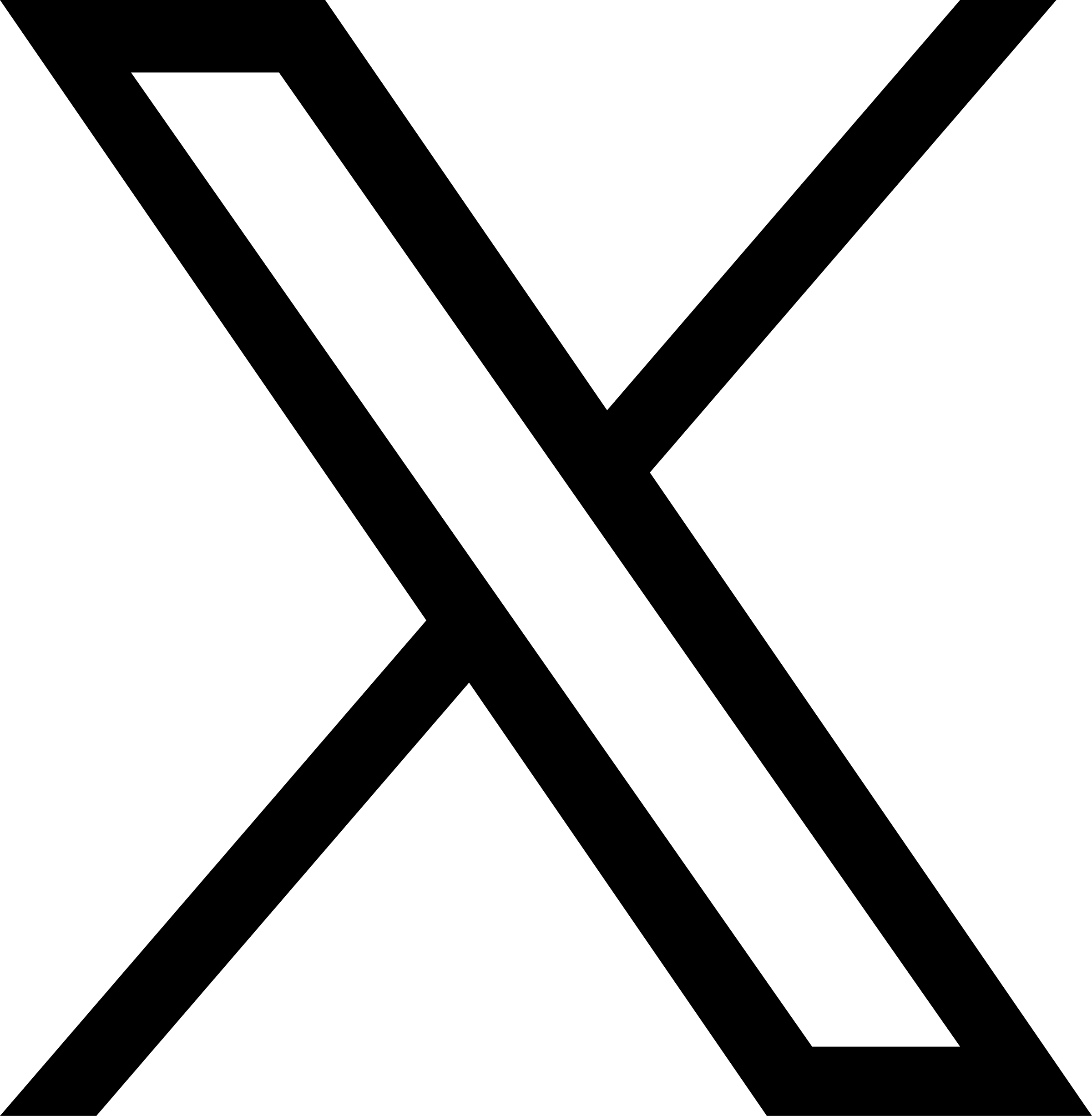

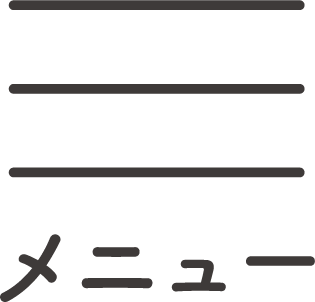

 2025年9月15日
2025年9月15日